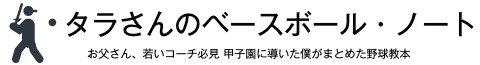こんにちはタラさんです。
こうすればキャッチボールが上手になる。
前回のスタンダードWとインバートWの解説は
いかがだったでしょうか。
よくわからなかったところもあったかと思います。
あくまで参考程度でかまいませんよ。
今回は「インバートL」について解説します。
もう少し理屈にお付き合いください。
1.背中側からの観察
1)インバートL(逆L字)

これは投手の背中側から見て「L」が逆さまになっている体勢をいいます。
着地の段階で腕がとトップまで挙がらず
前腕が地面を向いている体勢です。
すなわち、これも「逆W」と同様
前腕がトップで空を向いておりません。」
(コッキングしていない)
2)「ヒジから引き上げろ」の指導が招く動作
日本では「ヒジのしなり」をとても重視します。
そこで「ヒジから腕を引き揚げなさい」と指導します。
必然的にヒジを曲げた持ち上げ式のテイクバックをとることになります。
その結果この「逆L字」の体勢が生み出されました。
また、投球姿勢を作るのに足を上げて軸足一本で
「真っ直ぐ立ちなさい」と指導します。
このことによって両肩を結ぶラインは地面と平行になります。(マウンドの傾斜は考えないとします)
この立ち方がスタンダードになっています。
これが「逆 L字」を生み出す要因でもあります。
3)かつては肩を下げることで力を抜いていた
こうなったのはいつ頃からなのでしょうか?
戦前戦中も往年の名投手沢村選手に代表されるように
当時はマウンド上で肩を落とし
腕をそのままだらんと下げておくフォームが主流でした。
おそらく
当時はラジオ体操式(腕を伸ばしたテイクバック)が
スランダードで、その動作をスムーズに行うために
肩を下げて腕をリラックスさせていたのだと思われます。
この形、よく見ると0ポジションに腕があり
肩ヒジに無理のない安定した状態です。
当時は0ポジションの考え方はありません。
それでも理にかなったフォームを
練習の中で身につけていたのでしょう。
沢村投手とよく似ているのが桑田投手(現巨人コーチ)。
彼は盛んに「肩を落とせ」と言いっています。
PL時代の桑田を模したもの。
2.写真からあらためてテイクバックを考える
またと思われるでしょうが承知でお話します。
連続動作の一コマだけを見て形やフォームを真似する。
そのことで全体のバランスや身体の運動連鎖をブツブツと細切れにしてしまうのはそれこそ間違いを生みます。
下の写真を見てください。
まだ前足が着地してませんが
ここだけ見ると「逆W」の動き。
さらに、同じ投手の動きをみてみます。

残念ながら上と同じ投球の中での写真でないのですが
ここだけ見れば「スタンダードW」。
この投手はどちらのテイクバックを行っているのだろう、
と迷ってしまう人もいるかもしれませんね。
写真だけで判断してもよくわからないのが実際のところではないでしょうか。
投球動作はほんの一瞬の出来事。
写真の1枚だけで比較しても
すべてが同じタイミング、同じアングル、
同じ場所で撮影されたものとは限りません。
ですから、あくまで参考程度にするのが良いのです。
この選手は160km/hを記録した逸材。
今後170km/h出すのではないかと言われています。
一様、見かけ上の分類ではインバートWになるようです。もしMBLのコーチならフォーム改造に着手するのでしょうか?聞いてみたいところです。
3.良いフォームとは「身体に無理のない自然な動き」
フォームを見る場合、部分に囚われず
身体全体をどう使うか
ここにフォーカスして欲しいですね。
あくまで手足は部品です。
身体とはその部品を取り去って残った
胴体(体幹)のことを指します。
身体の動かし方は
まず胴体をいかに使ったら
効率の良い動きができるか
ここを考えることです。
胴体の動きに合わせて最後に手足くのですから。
けれども
どうしても目に付く手足の動きに指導の手を入れてしまうのが指導者の陥りやすい罠です。
「腕を内側にひねりを加えてヒジから引き上げなさい。
そうすればヒジから先をムチのように
しならせることができる」
このように口を酸っぱくして指導を行った結果
選手は意識的にヒジをあげる動きを覚えます。
(楽天 安楽投手)
上の写真のケースは典型的な「逆W」の例。
彼だって高校時代は甲子園で153km/hを出して一躍注目を浴びました。しかし投球過多がたたり、その後満足に投球できない時期もありました。結局は納得ゆく投球ができないまま最後の夏は予選敗退。卒業後プロへ進みましたが今のところ鳴かず飛ばずの状態になっています。
4.まとめ
2回にわたりテイクバックを見てきましょた。
やはりどこか動作に無理があると
その反動は必ずやってくるのではないでしょうか。
身体は正直ですから本来の動きとずれた動きをすると
必ず他の動きをすることで正しい動きに近くなるように反応します。(代償運動)
また筋力、柔軟性、バランス感覚にも個人差があります。
特にまだ身体の出来上がっていない小・中学校の年代では筋力不足が目立ちます。このことによりできる技術とうまく出来ない技術が出てきます。やはり身体の成長に合わせた技術指導がとても大事になりますね。
部分を意識をすればするだけ、自ずとそこに力が入ってしまうのです。でも、それを見た指導者は「力を抜け!」と声をかけます。すると今度は肝心なところで力が抜けたりしてしまう。何んとももどかしい。
練習はこなれた身体の動かし方を身につけるのが目的です。こなれた動きとは正しい順序で体を動かしていくことで生まれます。ですので、技術の修復はその部分だけの修正では根本解決にはなりません。間違った身体の使い方はその動作の前の動作の中に必ず要員があります。ですから全体の流れの中で見ていく視点、これを忘れないようにしてください。
最後までお読みくださりありがとうございます。
では、次回をお楽しみに。